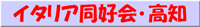| 26 | 25〜19 | 18 | 17 | 16 | 15/14/13 | 12/11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ←各年度の定例会報告へ |
2026年 定例会予定
2026年 総会・第1回定例会を次のとおり開催します。
- 日時:2月20日(金) 18:30〜20:30
- 場所:LaVita Mezzo Hall
- 定例会演題:「イタリア滞在夢物語 ―世界の見え方が360度(?)回転するお話―」
- 講師:中込照明会員
会員の中込照明さんにお話を伺います。長く高知大学理学部で教鞭を取られた中込さんの研究の原点となったイタリアのこと、そして、その研究の集大成である『唯心論物理学』についてお話しいただきます。世の中の見方が360度回転するという中込さんのお話を聞いて、不思議の世界に分け入ってみませんか?皆さまのご参加をお待ちしています。
講師からのメッセージ
今を去ること 40 年前、ふと気が付くと私は Camerino というイタリア中部の中世の姿そのままの丘の上の小さな町にいたのであります。発端はイタリアから京都での学会に来ていた先生に「暇しているなら俺の所に来い」といった感じで行くことになりました。そこは全くの別世界で、夢の中を楽しくさまよっている気分でした。その気分の中である閃きを得ました。そして後に同じような感じでポーランドに行くことになり、こちらも別世界でしたが、北国の閉ざされた落ち着きの中で夢の続きを見、Camerinoでの閃きを形あるものに仕上げることができました。
今回の定例会では、前半は Camerino で知り合った様々な人々を中心になるべく具体的に語りたいと思います。何しろ40年も前の出来事なので、記憶も定かではなく、たぶんに創作やその後に訪れたポーランドや Salerno での出来事とまじりあう可能性がありますが、ご容赦のほどをお願いいたします。後半は世の中の見方が360度回転するお話です。『唯心論物理学』すなわち「この世は心が全て」という主張ですが、なるべく夕食の席に合う内容にします。乞う御期待!
| 26 | 25〜19 | 18 | 17 | 16 | 15/14/13 | 12/11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ←各年度の定例会報告へ |